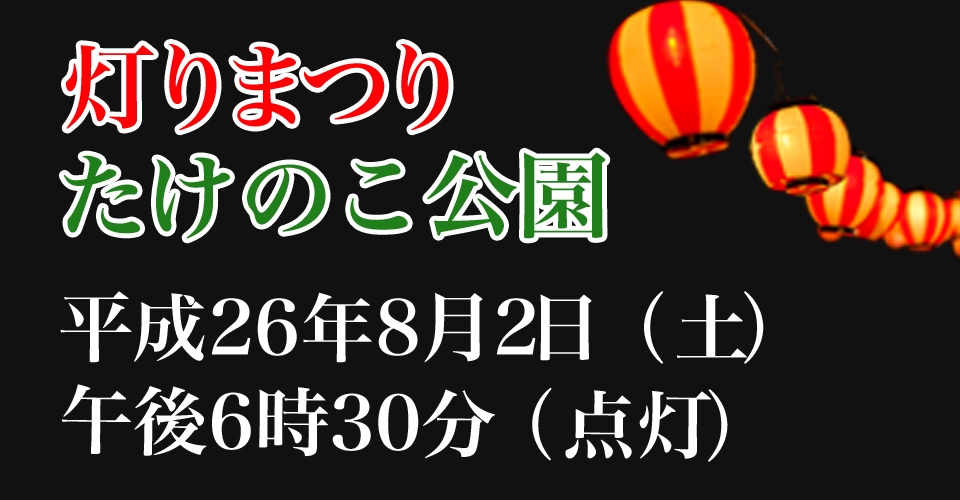ブランドビジネス
学生の手でブルーベリーのブランド商品を開発
小平市は日本で初めてブルーベリーを栽培した土地だが、小平産のブルーベリー関連の商品は、あまり知られていない。ブランドビジネスでは学生が独自に開発するブルーベリー商品を小平市の新しいブランド商品にすることを目指す。手を組むのは地域の隠れた名産品の販売で実績のある生産者直売のれん会だ。春休みには学生たちが、販売の経験を積むために石巻産の鯨の缶詰を駅前などで売り、300万円超える売り上げをたたき出した。最初はお客さんに、上手く声がかけられない学生も、お客さんと向き合ううちに、積極的に声が出るようになったという。

ドレッシング、チーズケーキ、プリン…。学生たちは様々なブルーベリー商品の企画を出した。企画の立案に向けて、さまざまな果物の商品の試食も行った。のれん会の森護商品企画室長は「学生ならではの感性で、自分には思いつかない案が出てくる」と驚く。学生が手掛けた商品が実際に販売され、それが地域の活性化につながるというのは得難い経験だろう。
プロジェクト担当の白鳥成彦先生は「自身をブランド化する手段も身に付く」と強調する。商品を売り込む手段やテクニックは自分を上手くアピールすることにつながる。就職活動にも直結するのだ。プロジェクトのメンバーでビジネス創造学部2年生の芳賀菜津紀さんは「社会人と一緒に働き、いろいろな業務を経験することで自分がどういう仕事に向いているのかが分かる」と手応えを感じている。
コールセンタービジネス
お客様の注文に敬語で対応
コールセンタービジネスは消費者と電話だけでやり取りしながら、商品の注文を受けたり、市場調査をしたりする仕事だ。このプロジェクトでは大手のテレコメディアと連携、実際に電話でやり取りをするコールセンター業務を経験するだけでなく、学生からお年寄りまで様々な人々からなるチームのまとめ役としての役割を担うこともできる。担当の姜徳洙先生は「どんな仕事か想像するのと実際にコールセンターに行って働いてみるのとでは、違いがあると思う。どんな所が良かったか厳しかったなどをしっかり学生1人1人に検証してもらいたい」と説明する。

プロジェクトのメンバーでビジネス創造学部2年の磯野友貴は実際にコールセンターの実務を経験した。「敬語が大変でした。『さようでございますね』など普段使わない言葉を使わなければならず、マニュアル通りの対応が精いっぱいでした」と振り返る。プロジェクトを通して、敬語を含めたコミュニケーション能力を向上させるのも一つの目標となる。また、テレコメディアに対して、どうやればお客様の満足度が上がるのか、効率的に仕事が進められるかについて学生の目線での改善策の提案も検討している。
コールセンターの現場は多くが女性で、将来女優さんを目指している人から主婦まで年齢や経歴もさまざま。こうした多様なチームをまとめ上げ、効率的な仕事を進めるリーダーシップを発揮することも学生たちに求められる。現場からリーダー役まで多くの仕事が経験できるのが魅力だ。
出版ビジネス
学生目線で伝える政治家インタビュー
出版ビジネスでは、学生が取材、記事を書くことに挑戦している。株式会社講談社と連携、同社インターネットサイト『現代ビジネス』での記事発信や書籍の出版を目指す。「長い期間出版社にいる私たちには出来ない、若者目線の記事を書いてほしい。そして、若者が買いたいと思える書籍の出版、新しい市場の開拓を目指す」と言うのは講談社の井上威朗さん。

学生をボランティアのように扱わず、このプロジェクトを通じて、稼げる記事を作成できる著者に育つことを求めている。その最初のステップとして、参院選を前に、自民党や民主党などの主要政党の国会議員へのインタビューを学生たちの手で行う。政治家から若者の心を掴み取る言葉を引き出だせるよう学生の視点を生かす取材をし、それを現代ビジネスの記事として発信することに挑戦する。秋からは、学生のやりたいことを生かした取材テーマの設定し、記事の作成を進めるという計画だ。
担当教員の小野展克先生も共同通信社で20年以上に亘って記者やデスクを務めた経験がある。「出版ビジネスのプロジェクトを通じて、自分の感性や見方に磨きをかけ、常に考え続け、それを自分の言葉で発信できるような学生になってほしい」という。仕事を任された記者と同じように学生を指導する。プロジェクトメンバーのビジネス創造学部2年生の山本圭祐君は「大学での授業は、インプットしたものを発信する機会が少ない。自分の言葉で記事を書くことで、人から聞いたことを自分の知にすることが出来る。このプロジェクトは知的生産の場であると思う」と話す。
インターネットビジネス
インターネットを利用したサービスの事業立案
「インターネット通販の企業へ行き、皆が何気なく使う『ネットショッピング』では、実際にどうお金が動いているのか、などを学ぶ」インターネットビジネスの担当教員の岡本潤先生は、このプロジェクトの特徴をこう指摘する。連携するのはインターネット通販大手で共同購入方式の活用などで業容を拡大しているネットプライスだ。

インターネットを活用したEコマース(電子商取引)の現場を学生たちが体験、自分達の目で特徴や問題点を見つけ、調査研究に取り組んでいる。実際に、学生たちの手でEコマースのビジネスを立ち上げる目標を掲げている。学生独自の視点を生かし、これまでにはない新たな市場をターゲットにした新ビジネスの誕生も夢ではなさそうだ。
プロジェクトメンバーのビジネス創造学部3年の天野修敬君は「『ただ何となく』面接に来る人間と『業界の良し悪し』を知っている人間、どちらが強いだろうかは言うまでもない。企業から求められる人間になりたい」と話している。
フードビジネス
将来フードビジネスや、飲食店関係のお店を開きたい人を求めている
飲食店を経営できる可能性は多くの若者に開かれている。その上、顧客に受け入れられれば、大きく成長するビジネスだ。このプロジェクトは、カフェやバーなどを幅広く展開しているプロントと連携、実際の店舗で接客などを経験するだけでなく、店舗経営などにも携わり、学生が店長の仕事にも挑戦する。

夏のインターンシップでは、茨城県にある古民家カフェを運営、学生の手でメニューの作成やお客さんへの対応、会計まで行う。売上が大きくなれば、海外の飲食店の視察などの研修も検討するという。
一方、プロントの店舗では、学生たちが新メニューの開発にもチャレンジする。他の飲食店のメニューを分析、利益を確保しながら顧客に受け入れられる値段の設定は、いくらか。そして若者に人気のメニューは何なのかを徹底的に追及する構えだ。最後は社長の試食で合格すれば、店舗のメニューとして登場する夢も叶う。
エンターテイメントビジネス
写真展への大学生1千人動員目指す
エンターテイメントビジネスは「どうすればお客様に感動を与えられるか、どんな価値を与えられるか」がテーマ。このプロジェクトでは読売新聞社文化事業部やミュージカル劇団Rカンパニーと連携して、このシンプルで奥の深いビジネスを体験することを目指す。「エンターテインメントビジネスは形がない見えないサービスだ。ディズニーランドなら土産を買わずに手ぶらで帰宅しても、幸せな気持ちが残り、また行ってみたいと思う。形として残らないサービスに価値があり、ニーズがあるのだ」と説明するのは担当の木幡敬史先生だ。

例えば読売新聞が主催するアンドレアス・グルスキーの写真展。グルスキーは、作品が現役写真家としては過去最高額の3億円で売れた実績を持つヒットメーカー。ただ、そんなグルスキーの写真展でも、どれだけ集客ができるかは未知数。特に大学生が、あまり写真展に足を運ばないのが主催者である読売新聞の悩みだ。そこでプロジェクトが掲げた目標は「写真展への大学生1千人の動員」。大学生の視点を入れて、どうやれば大学生を7月に始まる写真展に呼び込めるかの具体策を練り上げ、読売新聞に提案する計画だ。
「例えば美大生なら関心を持つかもしれない。ただ、美術系に関わっていない学校にも関心を広げないと目標は達成できない」と意気込むのはプロジェクトの学生でビジネス創造学部2年生の増田嵐樹君だ。どうやれば、写真展の魅力を大学生に伝え、会場に足を運んでもらえるのか―。学生はその裏方として知恵を出し、汗をかく。
観光ビジネス
「学生には、会議などにも参加してもらいその場で自分の意見をしっかりと指摘できる人になってほしい。若い人の視点からの意見も私たちは知りたい」と学生への期待を語るのはANA総研の主席研究員の森本全さん。

観光ビジネスは、ANA総研と組んで、学生が羽田空港のラウンジでの接客や顧客調査などの仕事を担う。仕事の中身は正社員と変わらない。空港という華やかな職場で、大きな責任と緊張感の中で、業務を体験しながら、観光業界について学べるのが特徴だ。春休み中のインターンシップでは最初は、緊張感からANA総研の社員の人たちに対しても声が出ず、挨拶すら上手くできない学生もいた。とても顧客に接客できる状況ではなかった。
担当の上原聡先生は「二週間もすると、ちゃんとコミュニケーションが取れるようになった」という。厳しい環境に、いきなり放り込まれるからこそ、課題が克服できる面もあるのだ。羽田空港のラウンジでは、飛行機の離陸を待つVIP顧客に対して、飲み物やおしぼりを提供するなど、心地よい待ち時間を過ごしてもらうための高度なサービスを実践する。体験の中で、おもてなしの極意を身に付けることを目指す。
事業創造ビジネス
後日掲載予定
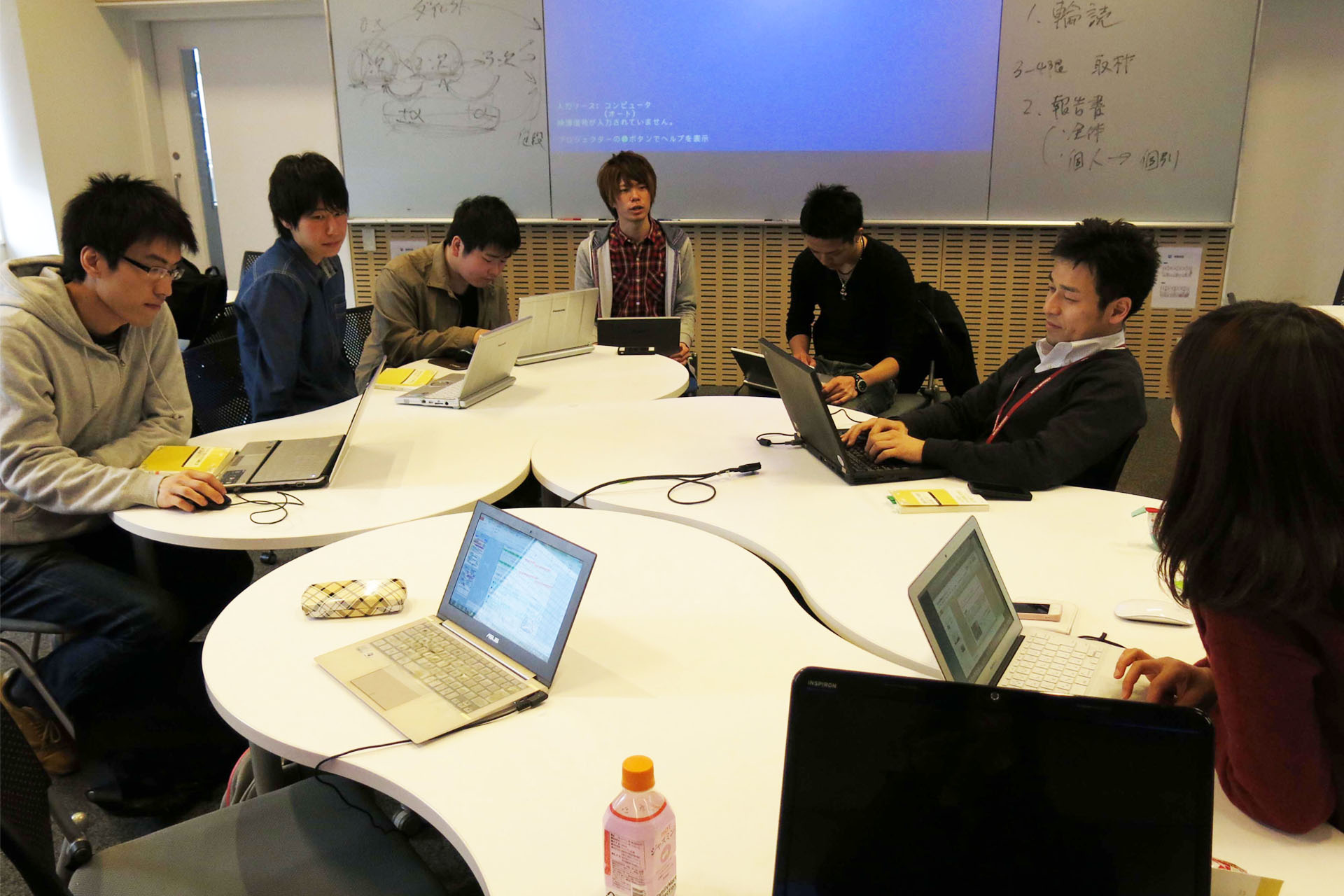
公益ビジネス
市民の生活に直結した問題を解決する
「自分で問題を発見し、解決できる人に育てたい」こう語るのは、ピースボートの竹内法和さん。ピースボートは、船で世界一周しながら国際協力に取り組む事業で知られるNGOだ。内田和夫先生が担当する「公益ビジネス」では、ピースボートなどと連携して、NPOやNGOのスタッフの職務を実際に体験する。

こういった所で働くことで、政府や企業と並ぶ非営利事業の必要性に気付く。インターンとして行く学生は「非営利組織の活動に興味はあったが、手を出せずにいた。実際に体験し、ごみ拾いでも社会貢献になるとわかった」と胸を張る。現在「ピースボール」という、サッカーを通じて国際協力を目指す企画のサポートを行う。
NPOは無償のボランティア活動であり、生活できる給与も得られないという印象がある。だが、「NPOの有給スタッフでも十分暮せるし、市民の生活に直結した問題を解決できる魅力あふれる仕事だ。」と内田先生は語る。