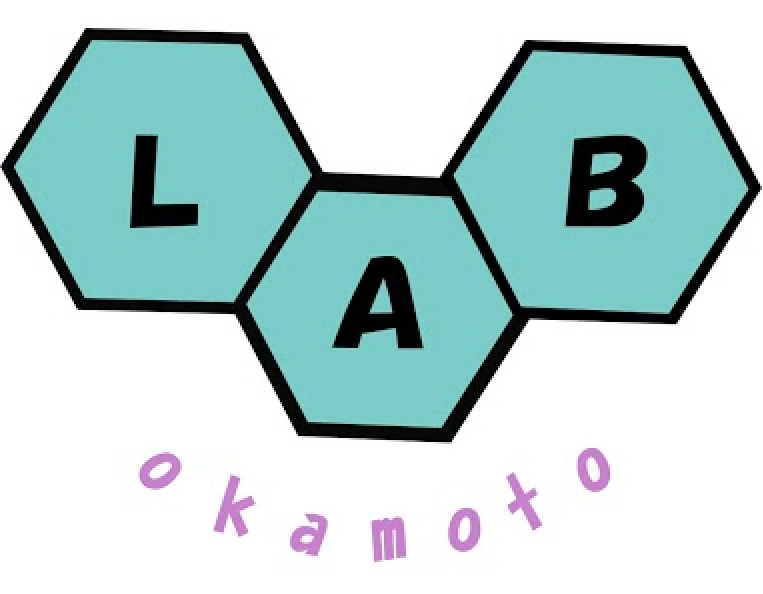灯りまつりとは?

灯りまつりの歴史
小平灯りまつりの由来は、古くから神社の祭事で灯ろうを参道、
氏子(祖神である氏神の子孫、または産土神(うぶすながみ)の鎮守する土地に住んでおり、
その守護を受け、それを祭る人々のことを指す)の家の門口に飾る風習からだと言われています。
小平市内には宵宮や祭礼の際に地口行灯を飾る風習があります。
今でも神明宮の祭礼の際などに、青梅街道沿いの家先に地口行灯が飾られている風景が見られます。
しかし、こうした灯ろうは時代とともに飾ることは少なくなってきています。
この伝統を後世に伝えていくため、
小平グリーンロードを舞台に新たな形で再現しようと平成18年に灯りまつりが始まりました。

地口行灯
地口行灯とは、ことわざや有名な芝居のセリフ、格言などを似た音の言葉に置き換えた「地口」を作り、
地口に合わせた滑稽(面白おかしい)画を描き、祭り用の行灯に仕立てたものです。
地口行灯をまつりに飾るのは、面白い絵や言葉を描いた華やかな行灯の灯りによる祭りの演出であると同時に、
祭礼時に飾られた行灯をひとつひとつ参拝者が見ては、その元句を当てたり、ひねりを楽しんだりすることにありました。
岡本研究会
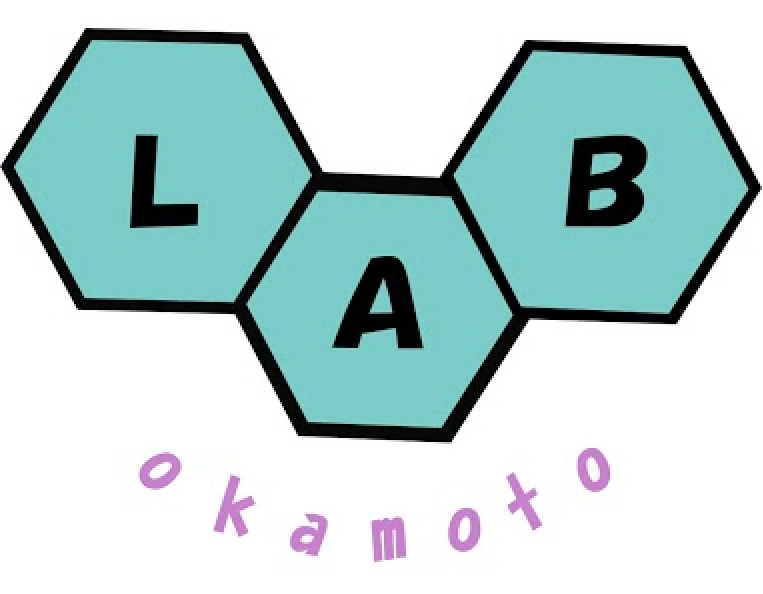
当サイトの運営を行う、岡本研究会のゼミ活動を紹介
c 2016 嘉悦大学ビジネス創造学部岡本研究会 ALL RIGHTS RESERVED.